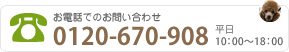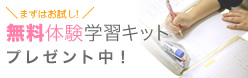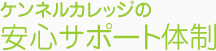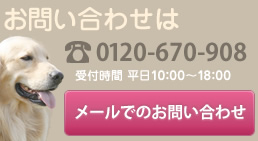ケンネルカレッジからの新着情報
ケンネルカレッジ
からの新着情報
先生からの回答の一例です(♯^▽^♯)ノシ
みなさん、こんにちは
ここ数日は、暖かい日が続くつくばですが明日からは気温が下がりそうです
スクーリングでお越しの皆様、暖かい服装でお越し下さいね!
専門学校の先生から「どんな回答が届くの?」というご質問を数件、
いただきましたので一例をアップしますね!
回答だけではなく、どのように質問すれば真意が伝わるのかも考えてみて下さい。
今回は比較的、短いコメントの回答を掲載させていただきます▽・山・▼
Q 犬の夜鳴きについて
A トレーナー講師 山内雅史
夜鳴きに関してですが、いただきました文面を読むと現在、正しく対処が出来ているなら、
分岐点に差し掛かっていると思います。
・以前は鳴くと布団に入れていた ・今は鳴くと相手をしなくなった
以上のことから、当初は寂しさ・不安などから鳴いていたが、鳴けば布団に入れてもらえることも
学習してしまった。鳴いても相手をしなくなったが、犬は鳴いても無駄だということが理解できて
いない・・・こういう状態であろうと推察します。
相手をしないように指導を受けた際、注意点として何か補足説明はありませんでしょうか?
無視をするようになってから夜鳴きがエスカレートしていると感じる節はありませんでしょうか?
経験則といたしまして、夜鳴きに限らず、無駄吠えや破壊行動などに対して「無視」による対処を
行なった場合、「一時的に」行動が悪化して見えるようになる場合があるように感じます。今まで
通用していた事(鳴けば布団に入れてもらえる)が、何故か通用しなくなったことで混乱が生じます。
ここで諦めておとなしくなるという流れが一般的に言われている内容だと思いますが、諦めて大人しく
なる前に「通用しなくなったので、もっと頑張ってみる」という行動に出る犬も存在するのです。
実際の状況を確認していませんので、あくまで推察ですが、現在はこのような状況だと思います。
今まで一緒に寝ていたのにそれができなくなったり、今まで一緒に家で暮らしていたのに、大きく
なって庭に出されるようになった場合等、相当なストレスに犬をさらすことになります。前肢をなめ
続ける行動もそのあたりが原因として考えられます。
鳴いても出さないという対処は続けるべきだと思いますが、ケージに入れて鳴き出す前や、大人しく
していられている時には優しく声をかけたりする対処も必要です。
鳴いても相手をしないならば、鳴かずにいる事は積極的にほめましょう、という考え方です。
災害時はもちろん、普段の生活でケージの中にいることが苦痛に感じるようでは、様々な面で
不都合が生じると思いますので、あきらめずに頑張りましょう!
以上です。
このようなやりとりを繰り返すと実技に関しても身に付いていくと思います。
受講生のみなさんはどんどん質問やご相談をなさって下さいね!